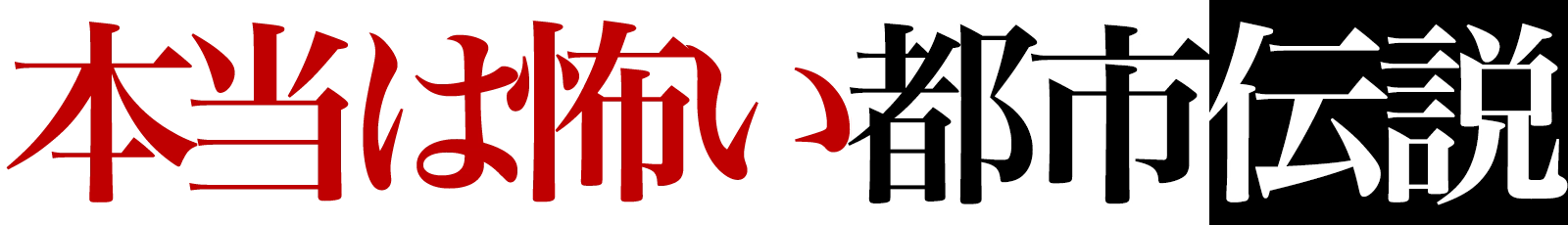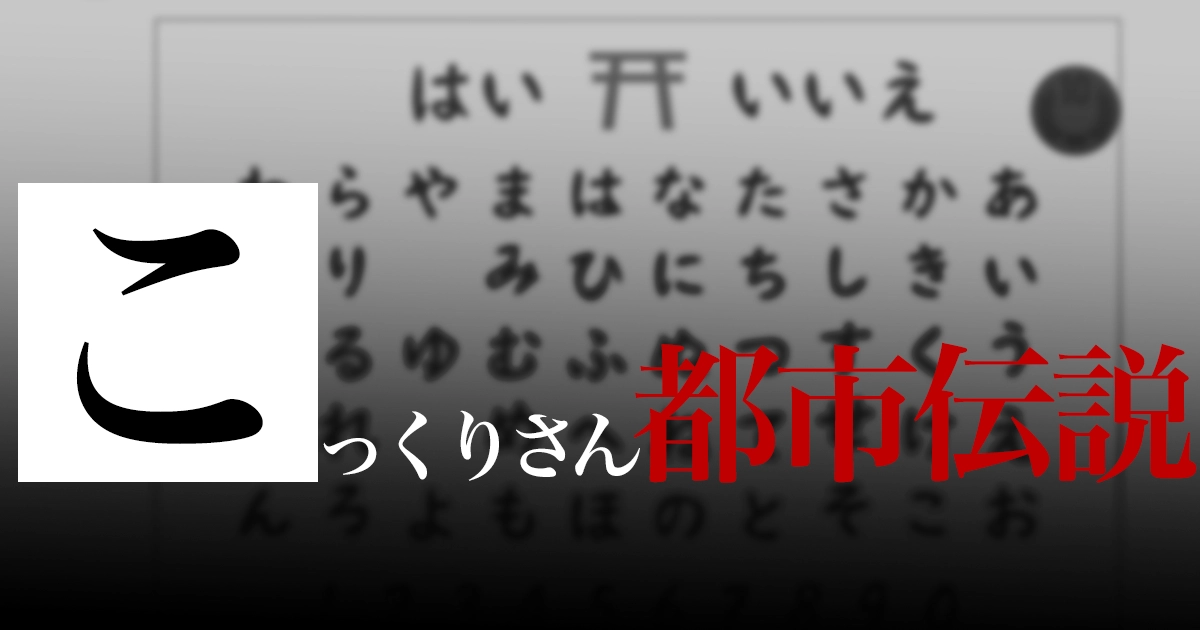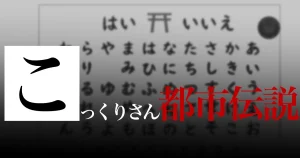「こっくりさん」は、1970年頃から小中学生の間で流行した占いで、10円玉と紙を使う、とても簡単でシンプルな遊びです。
しかし、こっくりさんは、時に社会問題となることがあります。
特に若者の間で流行すると、様々な問題が起こる可能性があります。
今回は、そんなこっくりさんの問題点について解説していきます。
こっくりさんが学校で禁止された理由
1970年代の大流行
1970年代、こっくりさんは日本全国の小中高生の間で爆発的に流行しました。
この現象は単なる遊びの域を超え、社会現象として注目を集めるようになりました。
学校や家庭での話題となり、メディアでも頻繁に取り上げられるなど、社会全体に大きな影響を与えました。
都市伝説や怪談の広がりを受け、こっくりさんを行った後、参加者が半狂乱になったり、霊に憑依されたりしたという噂が急速に広まりました。
これらの話は、事実というよりは都市伝説や怪談として伝播し、若者たちの間で恐怖と興味を煽る要因となりました。
実際の経験談と創作された話が混在し、真偽の判断が困難になっていきました。
こっくりさんは実話?死亡例は?
こっくりさんを行った後、死亡例は現時点ではありません。
しかし、一部の生徒に精神的な影響が見られるようになりました。
具体的には、
- 突然大声や奇声を発する
- 異常な行動をとる
- 幻覚や幻聴を訴える
などの症状が報告されています。
これらの症状は、恐怖心や暗示による心理的影響、あるいは集団ヒステリーの結果である可能性が高いとされていますが、参加者やその周囲に大きな不安を与える要因となっています。
そのため、一部の学校では「こっくりさん」の遊び自体が禁止されるまでに至ったのです。
スポンサーリンク
こっくりさんの社会問題
こっくりさんに関連する社会問題には、以下のようなものがあります。
- 心理的な影響による不登校
- 集団ヒステリーの発生
- 霊感商法の被害
これらの問題は、こっくりさんそのものが原因ではありません。
むしろ、人々の不安や恐怖心が引き起こす二次的な影響だと言えるでしょう。
イジメの発生
こっくりさんが学校で流行した際、イジメの道具として使われることがありました。
例えば、
- 教室で物がなくなった時、こっくりさんで犯人捜しをし、名指しされた子がクラス全員からイジメを受ける。
- 1980年には、大阪府で中学2年生の女子がこっくりさんの「お告げ」を信じ、同級生を集団リンチする事件が発生。
これらの問題により、多くの学校でこっくりさんが禁止されるに至りました。
スポンサーリンク
心理的影響による不登校
こっくりさんの体験が、子どもたちに強い心理的影響を与え、不登校の原因となることがあります。不登校の子どもの心理には以下のような特徴があります。
- 自信が持てない
- 人間関係が怖い
- 学校や家族に反発したい
- 将来に漠然とした不安がある
こっくりさんの怖い体験が、これらの心理状態を悪化させる可能性があります。
集団ヒステリーの発生
こっくりさんを行っている最中に、集団ヒステリーが発生する事例が多く報告されています。
集団ヒステリーの特徴は、
- 特定の集団が強い不安や恐怖にさらされたときに発生
- 集団の構成員全体にパニックや妄想が広がる
- 子どもや若い女性の間で起こりやすい
こっくりさんには元々オカルト的な要素があるため、参加者が恐怖や不安を感じやすく、集団ヒステリーの引き金になりやすいのです。
これらの社会問題は、こっくりさんそのものが直接の原因ではなく、人々の不安や恐怖心が引き起こす二次的な影響だと言えます。しかし、その影響の深刻さから、学校や社会で問題視されるようになりました。
スポンサーリンク
現代版こっくりさん「チャーリーゲーム」
特に、教育現場では、こっくりさんが深刻な問題として認識されるようになりました。
2015年に問題となった現代版こっくりさんとして、「チャーリーゲーム(Charlie Charlie Challenge)」があります。
こっくりさんの現代版とも言えるチャーリーゲーム(ペンシルゲーム)が中高生の間でブームとなり、授業中や休み時間に挑戦する生徒が続出しました。
これにより、学習環境が乱れたり、生徒間のトラブルが発生したりするなど、複数の中学校で特別な生徒指導が必要となるほどの事態に発展しました。
宗教的懸念
こっくりさんの流行は、宗教界からも懸念の声が上がっています。
特にアメリカのカトリック系高校では、司祭が「悪魔と遊ぶな」と生徒へ警告する事態も起きています。
これは、こっくりさんが霊的な存在を呼び出す行為と見なされ、宗教的な観点から問題視されているためです。
日本でも、一部の宗教団体がこの行為に対して警鐘を鳴らしています。